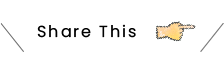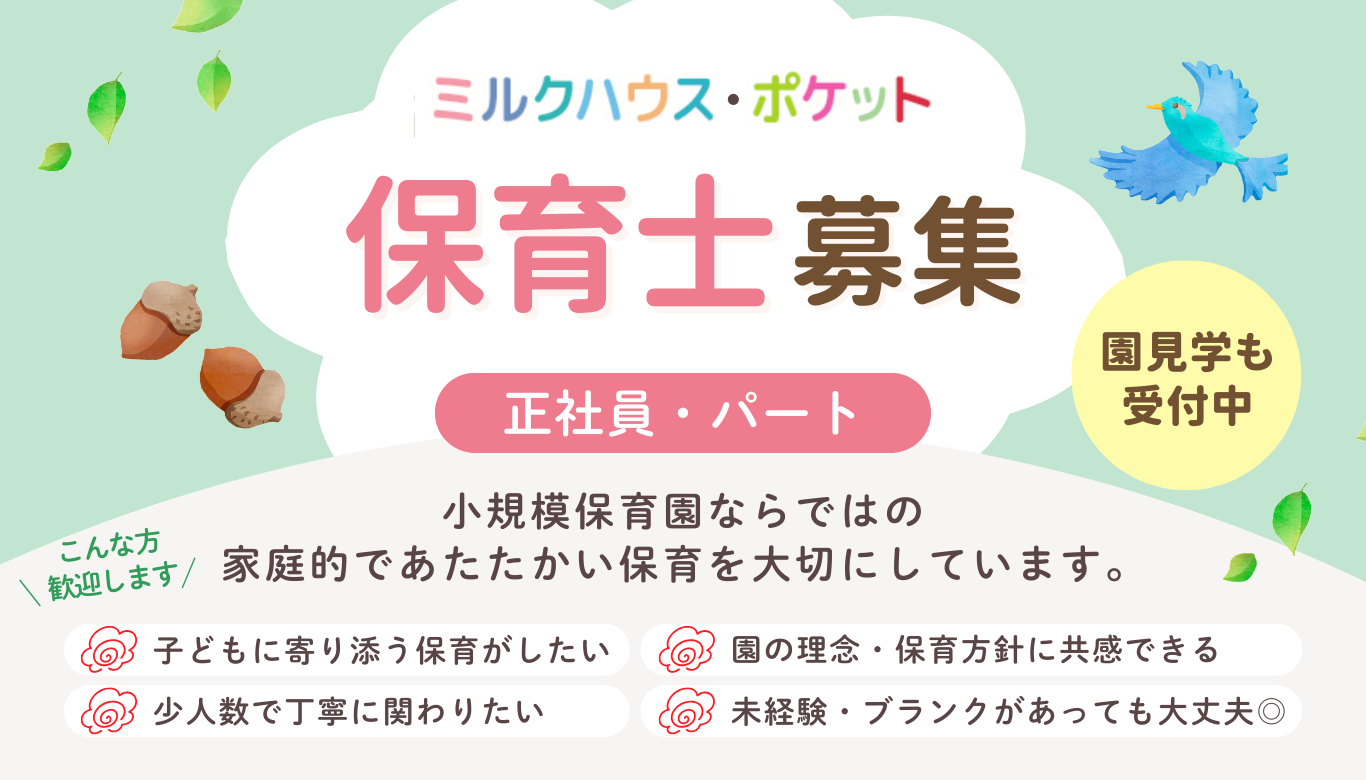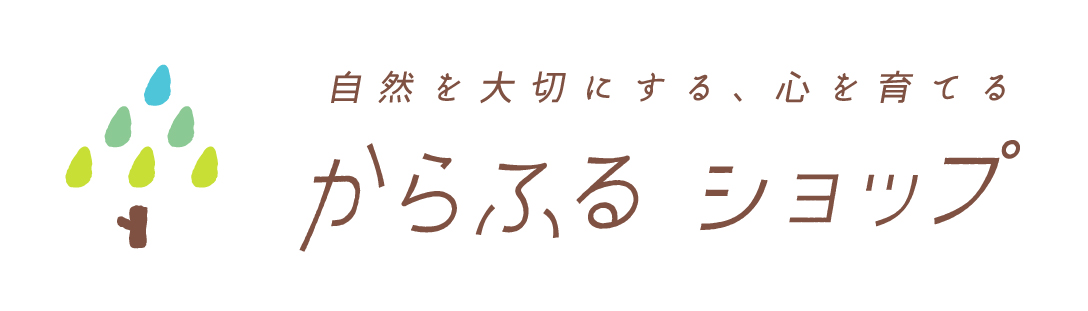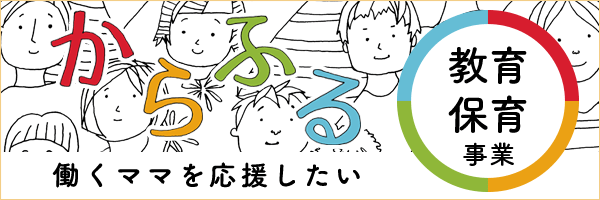365日からふるに子育て!第76回 冬にそなえて、親子で“カラダを守る力”を育てよう

「次世代へ健やかな未来をつなぐ」
ウェルサポのフレンドナース菊池です。
冷たい風が吹きはじめ、空気が乾燥してくると、ウイルスが元気になる季節がやってきます。学校や園でも咳や鼻水の音が聞こえ始め、体調を崩すお子さんが増えてくる時期です。
「うがい・手洗いだけでは防ぎきれないのでは?」と感じる方も多いでしょう。
けれども、感染症に強いカラダづくりは、日々の積み重ねでしっかりできます。
今年の冬は、カラダの中から免疫力を高めるケアと、親子で一緒にできる感染対策を意識してみましょう。
毎日の習慣がそのまま、子どもの「自分のカラダを大切にする力」につながります。
1. これからの季節に多い感染症と症状
まずは、どんな感染症が増えるのかを知っておきましょう。早めの気づきが回復を早めます。
冬にかけて多いのは、次のような感染症です。初期症状を見逃さず、早めに休息をとることが大切です。
風邪
のどの痛み、鼻水、くしゃみから始まり、進行すると咳や高熱に。
水分補給をしっかり行い、カラダを温かく保ちましょう。
インフルエンザ
突然の高熱(38度以上)と関節の痛み、全身のだるさが特徴。
高熱が続くときは早めの受診を。家庭内でもマスクや換気を徹底しましょう。
RSウイルス感染症
乳幼児に多く、初期は鼻水や微熱、悪化するとゼーゼーとした呼吸や息苦しさが見られます。
小さな子どもは日ごろから呼吸音を意識して聞いておくと、変化に気づきやすくなります。
感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)
吐き気や嘔吐、下痢、発熱など。家族間でうつりやすいので注意が必要です。
トイレの後やおむつ替え後の手洗いを徹底しましょう。
感染症の初期は「なんとなくだるい」「少し食欲がない」といった小さなサインが多いです。
お子さんの“いつもと違う”様子に気づけるのは、日々見守る親の大きな力です。
症状が軽いうちに気づいて休ませることが、結果的に回復を早め、家族への感染も防ぎます。

2.対策① カラダを強くする:免疫力アップの基本
感染を防ぐ第一歩は、「うつらないカラダ」をつくること。
食事・運動・睡眠がその土台になります。
食事:カラダをつくる“材料”を整える
免疫細胞の働きを助けるには、たんぱく質・ビタミン・ミネラルが欠かせません。
ごはん・肉・魚・卵・野菜・きのこ・発酵食品を組み合わせ、バランスよく食べましょう。
- 朝食を抜かない:カラダを温め、代謝をスタートさせる大切なスイッチ。
- 発酵食品をとる:ヨーグルトや味噌汁、納豆は腸内環境を整え、免疫を支えます
- 旬の食材を使う:冬野菜(大根・白菜・ねぎ)はカラダを温め、ウイルスに負けない力を育てます。
子どもと一緒に「何入れようか?」と献立を考えるのも、食への関心を高め、自分のカラダを大切にする一歩です。
運動:カラダを動かして“温める”
カラダを動かすと血流がよくなり、体温が上がります。体温が1度上がると免疫力は数倍になるともいわれます。
外遊びが減る冬こそ、意識してカラダを動かす時間を作りましょう。
- 朝のラジオ体操や親子ストレッチ
- 公園でのかけっこやボール遊び
- 雨の日は室内で風船バレーやタオル引き
- 「一緒にやろう!」と声をかければ、子どもは遊びの延長で自然と運動量を増やせます。
睡眠:回復と成長のゴールデンタイム
- 夜更かしや不規則な生活は免疫力を下げます。
- 夜9時には布団に入れるよう、夕食やお風呂のリズムを整えましょう。
- 寝る前の絵本タイムや「今日もよく遊んだね」と声をかける習慣は、心の安心にもつながります。
食事・運動・睡眠という当たり前の習慣こそ、最大の免疫ケアです。
毎日の積み重ねが、病気に負けないカラダを育てます。

3.対策② カラダを守る:感染から身をまもる工夫
ウイルスを「持ち込まない」「ひろげない」ために、家庭でできる予防習慣を確認しましょう。
手洗い・うがいは“自分のカラダを守る”第一歩
- 石けんで20秒以上、指先や指の間手首までしっかり洗うのが基本です。
- 「ハッピーバースデー」の歌を2回歌うと、ちょうど20秒です。
遊びながら、子どもが自分で続けられる習慣にしましょう。
うがいも、最初は水だけで十分。自分の手でコップを持ち、うがいをする経験が「できた!」という自信になります。
咳エチケット・マスク・換気を一緒にしよう
- マスク:人の多い場所では親が率先して着ける姿を見せることで、子どもも自然とまねします。
- 咳エチケット:咳やくしゃみは、手で押さえず腕の内側で。遊びの中で練習しておくと、いざというときに身につきます。
- 換気:暖房を使う冬ほど、1時間に1回の換気を。窓を2か所開けると空気が循環しやすくなります。親が声をかけるより、「一緒にやってみよう」と行動で示すことが、子どもの自立を育てる近道です。
持ち帰らない・うつさないための家庭習慣
- 帰宅後の流れを「ルール」ではなく「親子の合図」にしてみましょう。
- 玄関で「ただいま」のあとに手洗い・うがい
- カバンを定位置へ
- 洗面所で鼻をかむ、うがいをする
- 手を拭いたら「できた!」のハイタッチ
この流れが自然にできるようになると、感染対策だけでなく生活の自立にもつながります。
感染対策を「やらされること」から「自分でできること」を親子で取り組むことで、予防行動そのものが学びと成長の時間になります。
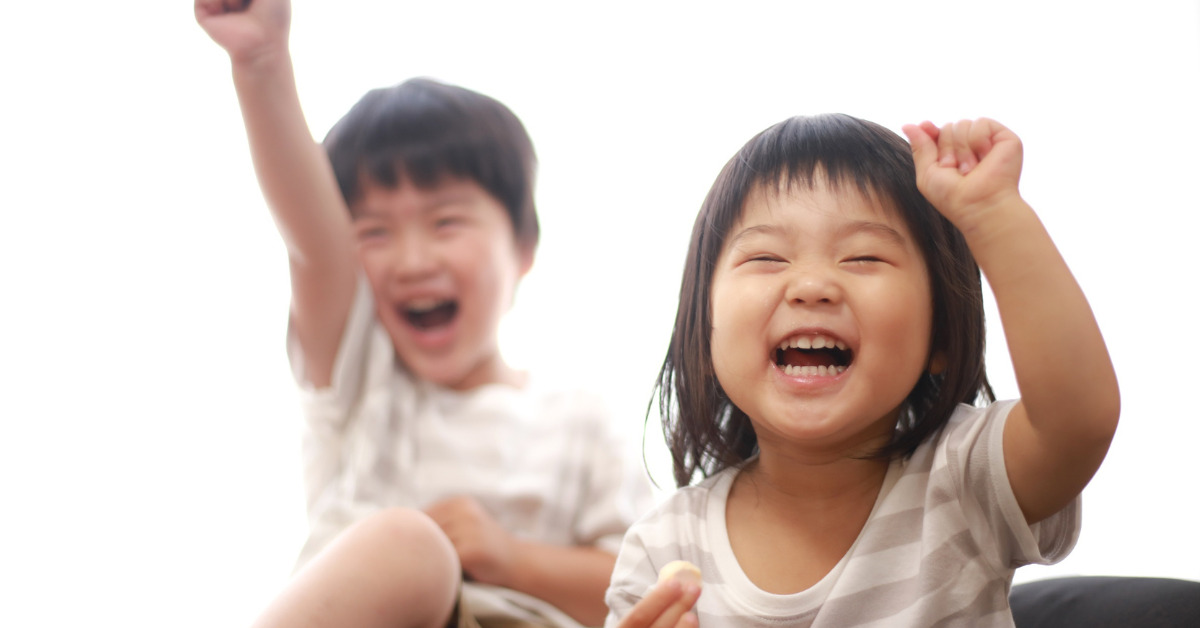
4.親子で“できた!”を重ねて冬を元気に
冬の体調管理は、子どもが自分のカラダを知るチャンスです。
感染症の季節でも、カラダの中から強く、外から守れる親子であれば安心です。手洗いひとつ、食卓での会話ひとつも、親子の健康づくりの時間です。
「今日はどんな運動した?」「どんなごはんがカラダを元気にするかな?」そんな声かけを通して、子どもが少しずつ自分のカラダに関心を持つようになります。
カラダを大切にする気持ちを育てることは、健康だけでなく、将来の自立にもつながる大切な土台です。
冬を迎える準備は、“カラダを守る力”を育てるチャンス。
親子で“できた!”を積み重ねながら、健やかに冬を乗り越えましょう。
<ウェルサポについて>
臨床経験豊富なフレンドナース(かかりつけナース)が、利用者自身の身心の相談はもちろん、子育てや介護、ご家族の健康に寄り添ったオンラインのチャット相談を行っています。他にも、オフラインで行う定期訪問サポートやアテンドサポートなど行っています。社会福祉士、健康運動指導士、助産師、管理栄養士などの専門家や他サービスとも連携して、利用者とそのご家族の「自分らしい健やかな暮らし」をサポートしています。
一般財団法人ウェルネスサポートLab(ウェルサポ)情報
webページ : https://www.wellsuppo.or.jp
メールアドレス:info@wellsuppo.or.jp
電話番号:092-231-9762
〇ライター紹介

菊池 美保(きくち みほ)
看護師歴20年。「祖母らしい最期」を目の当たりにしナースの道へ。福岡赤十字病院17年在籍中に様々な科で実績を積み、病棟管理職、病院運営などを経験。「患者さんファースト」の医療をモットーのスーパージェネラリスト。
好きなこと:筋トレ、キックボクシング、スキンケアやコスメリサーチ
苦手なこと:細かい作業、ずっと座っていること
ライター紹介